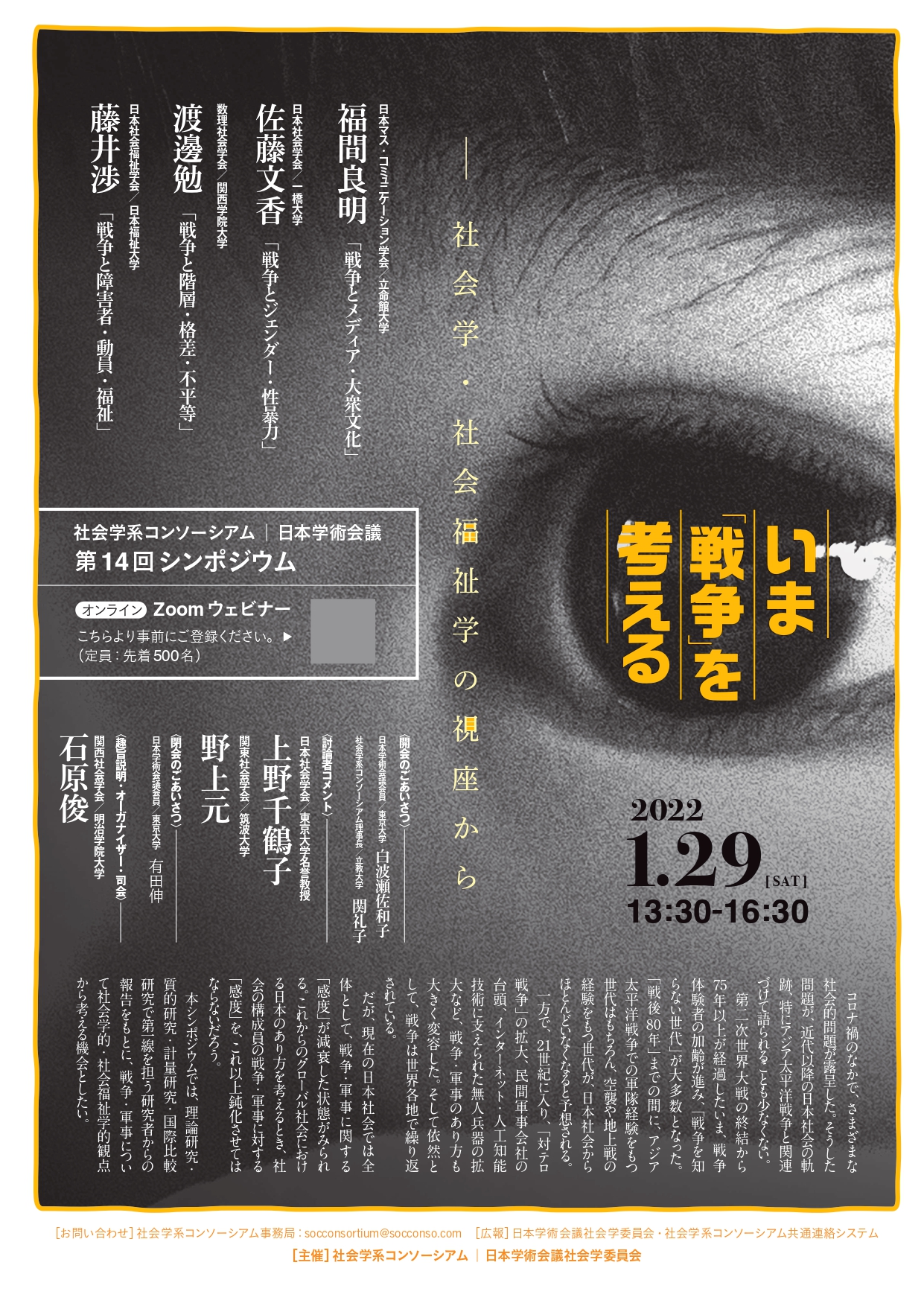テーマ 「ケア/ジェンダー/民主主義」
趣旨
社会学が新たな学問として登場したとき,隣接分野との対話はきわめて重要な意義を持っていました。その後,社会学は高度に専門化しましたが,「社会学とは何か」「社会学だからできることは何か」が問われるいま,隣接分野との対話を再び活性化させる必要があるように思われます。こうした問題関心から,2020年度より,学会大会で,招待講演を開催してきました。
第71回大会(2020年10月10日)は,思想家の内田樹さんに,「コロナ時代の日本を考える」と題して講演いただき,伊地知紀子さん(大阪市立大学,研究活動理事)の司会のもと,伊藤公雄さん(京都産業大学,常任理事)とのトークセッションを展開しました。
第72回大会(2021年6月5日)は,文化人類学者の松村圭一郎さん(岡山大学)に,「『わたし』をとおして世界を探求する~社会学と人類学の間の藪をつついて蛇をだす~」と題して講演いただき,工藤保則さん(龍谷大学,研究活動理事)の司会のもと,松浦雄介さん(熊本大学)とのトークセッションを展開しました。
次回第73年大会(2022年5月29日)は,岡野八代さん(同志社大学)をゲストに招き,招待講演を開催します。岡野八代さんは,西洋政治思想史・フェミニズム理論を専門に研究されている政治哲学者です。『フェミニズムの政治学――ケアの倫理をグローバル社会へ』(みすず書房,2012年)などの著書でご存知の方も多いと思います。ケアを中心的なコンセプトとして研究をされており,著名なケア研究者であるジョアン・C・トロントとコラボした『ケアするのは誰か? 新しい民主主義のかたちへ』(白澤社,2020年),社会学者の牟田和恵さん・丸山里美さんとの共著『女性たちで子を産み育てるということ――精子提供による家族づくり』(白澤社,2021年)を刊行され,また,世界的に話題の『ケア宣言』(大月書店,2021年)を翻訳し刊行されました。
今回の招待講演では,『世界』2022年1月号に発表された「ケア/ジェンダー/民主主義」をベースに講演いただく予定です。講演の内容は,大会シンポジウムのテーマにも深く関連しています。そこで,招待講演に続けて,シンポジウムを開催することとしました。岡野さんには,シンポジウムの討論者もあわせてつとめていただきます。どうぞご期待ください。
日時
- 5月29日(日曜日)13時00分~14時00分
講演者
- 岡野八代(同志社大学)
司会
- 岡崎宏樹(神戸学院大学)
(研究活動委員長 岡崎宏樹
研究活動理事 落合恵美子)